商品の第一印象を決定づけるパッケージデザインは、売上に直結する重要な要素です。しかし、効果的なパッケージデザインの作り方がわからず、悩んでいる企業の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、パッケージデザインの基本的な作り方から具体的な作成手順までを、わかりやすく解説します。デザイン制作のポイントを押さえて、商品の魅力を最大限に伝えるパッケージを制作しましょう。
- パッケージデザインの2つの制作方法
- パッケージデザインの作成手順
- パッケージデザイン制作時の注意点
パッケージデザインの作り方
パッケージデザインの作り方

パッケージデザインは商品の魅力を伝え、消費者に自社ブランドをアピールする重要な役割を担っています。効果的なパッケージデザインを作成すれば、売上やブランド認知度の向上が期待できるでしょう。
パッケージデザインの作り方には、大きく分けて「自社で作成する方法」と「デザイン会社に依頼する方法」の2通りがあります。それぞれの特徴を理解し、自社に適した方法を選びましょう。
自分で作成する
自分で作成する
Illustratorなどのデザインソフトやテンプレートサービスを活用して、社内でデザインを作成する方法です。デザイン会社に依頼する場合に比べて作成コストがかかりにくく、取り入れたいイメージや要素を自由に組み込める点が魅力です。
一方で、作成に必要なツールや作業環境を整えるのに初期コストがかかる、ゼロからデザインを作成する場合は技術の習得に時間がかかるといった点に注意しましょう。特に、社内にデザインの知見を持つ人材がいない企業だとハードルが高めの方法です。
工数やクオリティを考慮し、自社で対応可能かどうかを事前に見極めましょう。
デザイン会社に依頼する
デザイン会社に依頼する
もうひとつの方法は、専門のデザイン会社に依頼することです。自社のイメージや商品の特徴をもとに、クオリティの高いデザインを仕上げてもらえます。
プロのデザイン会社に依頼するメリットは、訴求力のあるレイアウトや最新トレンドの反映といった、専門的な視点を取り入れられることです。さらに、マーケティング戦略を踏まえた提案や、競合との差別化を意識したデザインにも対応してくれるため、売上アップにつながる可能性が高まります。
ただし、依頼料やサンプル制作費が発生するため、社内で自作する場合と比べてコストは高くなりがちです。費用対効果を見極めながら、自社の商品に合ったデザインを提案してくれる信頼できる会社を選びましょう。
パッケージデザインの作成手順
パッケージデザインの作成手順
パッケージデザインは、商品の売れ行きに大きく影響します。そのため、感覚で進めるのではなく、段階を踏んで丁寧に作り込むことが重要です。手順をしっかり押さえれば、ターゲットに響く魅力的なデザインに仕上げることができます。
パッケージデザインの具体的な作成手順について、以下より詳しく解説します。
目的・ターゲットからコンセプトを設定する
目的・ターゲットからコンセプトを設定する
パッケージデザインの設計においては、最初に「誰に」「どんな目的で」商品を届けたいのかを言語化するのが大切です。この段階が曖昧だと、デザインの方向性も定まらず、完成度に影響が出てしまいます。
以下の表は、30代女性向けのスムージー商品を想定した設定例です。
| 項目 | 内容例 |
| 目的 | 忙しい朝の「時短栄養補給」として提案し、定期購入へつなげる |
| ターゲット | ・東京都内在住・30代前半の女性、IT企業勤務 ・通勤が長く、朝食はコンビニ頼り。Instagramで「腸活」や「朝活」をチェックする習慣あり |
| 商品コンセプト | ・慌ただしい朝でも1本で栄養チャージ ・手間なくキレイ ・乳酸菌×フルーツ×スーパーフードの“飲む”美容習慣 |
ターゲット像をできるだけ具体的に言語化することで、訴求すべきポイントや必要なデザイン要素が見えてきます。そこから商品コンセプトを絞り込めば、ブレのない一貫したデザインを作成しやすくなるでしょう。
調査を通じて生活者ニーズを把握する
調査を通じて生活者ニーズを把握する
ターゲットが決まったら、ターゲット層が実際にどのような価値観や課題感を持っているのかを調査しましょう。企業の仮説だけでパッケージを設計してしまうと、生活者の本音とズレが生まれ、心に響かないデザインになる可能性があります。
調査では、以下の「定量調査」と「定性調査」を組み合わせるのが一般的です。
| 調査方法 | 例 |
| 定量調査 | ・アンケート(オンライン・紙) ・Webリサーチ(パネル調査など) ・会場調査(CLT) ・ホームユーステスト(HUT) |
| 定性調査 | ・グループインタビュー ・デプスインタビュー(1対1の深堀り) ・行動観察(エスノグラフィ) ・SNS分析や日記調査 |
例えばスムージーの場合、「忙しい朝でも手に取りやすい形は?」「ひと目で“ヘルシー”と感じられる色や表現は?」といった問いを立て、実際の生活者の声を収集します。得られたデータは、ターゲットに刺さる要素の裏付けとして活用しましょう。
なお、デザイン会社によっては調査まで請け負ってくれるケースもありますが、自社でも事前に調査を行っておくことで、打ち合わせがスムーズに進み、差別化ポイントの共有もしやすくなります。
収集した情報からアピールポイントを深堀りする
収集した情報からアピールポイントを深堀りする
調査で得られた情報をもとに、商品のターゲットや目的、コンセプトの解像度をさらに高めていきましょう。市場調査や競合分析を行うことで、似たような商品との違いや、効果的なデザインの方向性が見えてきます。
具体的には、競合他社の商品からパッケージデザインの色や形、訴求メッセージの見せ方などを分析し、自社商品がどこで差別化できるのかを検討します。この段階で明確になった差別化ポイントは、デザイン制作の際に重要な指針となるでしょう。
パッケージデザインに落とし込む
パッケージデザインに落とし込む
情報収集と分析が一通り終わったら、これまで整理してきた内容をもとに、実際のデザインに反映していきます。素材や形状はもちろん、売り場での見え方、季節感、トレンド、使いやすさなど、さまざまな視点から、生活者にとって価値あるパッケージを設計しましょう。
印象を左右する視覚要素を設計する
印象を左右する視覚要素を設計する
最初に色やフォント、レイアウト、コピーなど、視覚的要素によって第一印象をどのように設計するかを考えます。キャッチコピーの配置や文字サイズのバランスも、購買意欲に大きく影響します。
例えば、やさしさや安心感を伝えたい商品であれば、ベージュやパステルなどの柔らかい色調に、丸みのあるフォントを組み合わせると、全体の印象が統一されるでしょう。一方で高級感を演出したい場合は、黒や深いネイビーにゴールドを加えるのがおすすめです。
ラフスケッチを描いて構成を整理し、複数案を比較しながら、視認性や訴求力の高いデザインに近づけていきましょう。
使用シーン・売り場環境をデザインに反映させる
使用シーン・売り場環境をデザインに反映させる
商品がどこで、どのように使われるかを想定したうえで、デザインに落とし込むことも大切です。朝の忙しい時間に飲むスムージーであれば、「すぐ手に取れる」「軽くて持ち運びやすい」といった要素をパッケージにも取り入れると効果的でしょう。
また、どの売り場に陳列されるかを想定する必要もあります。スーパーマーケットの棚に並ぶ場合は、中段に置かれた際に目に留まりやすいかどうかを意識しましょう。ECサイトで販売する場合は、サムネイル画像でも情報が伝わるわかりやすさが求められます。
消費者の体験視点で考えると、魅力的なパッケージデザインにつながるでしょう。
季節感・トレンド要素をデザインに反映させる
季節感・トレンド要素をデザインに反映させる
季節感やトレンドを意識したパッケージデザインは、共感を呼びやすく、話題性にもつながります。例えば、春には桜を連想させる淡いピンク、夏には爽やかなブルーなど、季節に合ったカラーやモチーフを取り入れると、消費者の感性に自然と寄り添えるでしょう。
また、近年ではSDGs配慮、ナチュラル志向など、時代背景に合わせたデザインニーズも注目されています。とはいえ、一時的なブームに流されるのではなく、自社商品のコンセプトと整合性があるかどうかを見極めたうえで、柔軟にトレンドを取り入れることがポイントです。
競合商品のパッケージ事例や、SNSで話題になっているデザインを参考にすれば、今の市場に合ったアプローチが見えてくるでしょう。
素材と形状から商品の価値を設計する
素材と形状から商品の価値を設計する
パッケージの素材や形状は、商品に込めた価値観や世界観を伝える重要な要素です。保存性や物流条件などの実務要件に加え、「商品を通じてどんな価値を届けたいか」を軸に設計していくとよいでしょう。
例えば、「自然由来」「無添加」といった価値を重視する場合は、クラフト紙やバイオマス素材などを採用すると、見た目や手触りからその世界観が伝わります。一方で、スタイリッシュなライフスタイルを意識した商品であれば、光沢のあるラミネート素材やアルミパウチなどを使えば、都会的な印象を強調できるでしょう。
試作品を作成する
試作品を作成する
すべての設計が整ったら、試作品としてデザインの印刷を行います。パッケージ印刷では、プラスチックフィルムやアルミ蒸着紙などの特殊素材に対応した印刷技術が必要となるため、専門の印刷会社に依頼するのが一般的です。
印刷前には、最終的なデザインチェックを忘れずに行いましょう。情報を詰め込みすぎて視認性が落ちていないか、第三者の目で確認することも大切です。デザインを外部に委託した場合は、初期のコンセプトとずれていないか、訴求ポイントがしっかり伝わっているかを細かくチェックしましょう。
あわせて、実物を手に取ったときの重量感や質感も確認し、使い心地や操作性に違和感がないかも確認しておくと安心です。
納品された印刷物を確認する
納品された印刷物を確認する
印刷工程が完了したら、印刷物の納品と仕上がりの確認を行います。納品されたパッケージが、事前のデザインデータと一致しているかをチェックしましょう。色味や形状、サイズ、使用されている素材など、想定どおりの仕上がりになっているか、細かな点まで目を通すことが大切です。
また、納品数量や梱包状態、納期なども合わせて確認し、不備があれば早急に印刷会社と調整を行いましょう。印刷物が実際に使用される現場で問題なく運用できるかどうかまで見届ければ、パッケージデザインの制作プロセスが完了します。
品質に問題がないと確認したら、本格的な商品展開へと進めます。
パッケージデザインを作る際の注意点
パッケージデザインを作る際の注意点
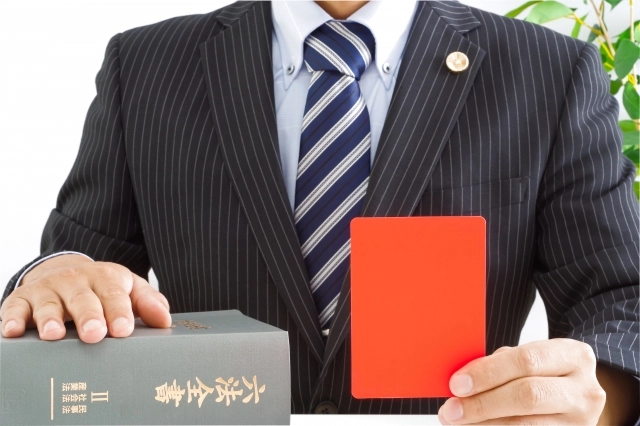
パッケージデザインを進める際には、関連する法規制を必ずご確認ください。例えば、食品には「食品表示法」、化粧品や医薬部外品には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」が適用されます。
また「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」では、誇大な表現や誤解を招く表示が禁止されています。特に健康食品や美容関連の商品では、効果があるように見せかける表現や医薬品と誤認される表現は厳格に規制されているため、細心の注意が必要です。
さらに、食品や化粧品など体に直接触れる商品では、内袋や容器に「食品衛生法」に基づく安全基準を満たした素材を使う必要があります。法規制や義務について確認のうえ、内容物や原産国、賞味期限、成分表示といった必須項目も、正しくデザインに組み込むことが求められます。
商品の安全性を保ち、法的リスクを避けるためにも、使用環境や法規制をふまえた設計を心がけましょう。
関連法規について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
まとめ
まとめ
パッケージデザインは、自社で作成する方法と、専門のデザイン会社に依頼する方法があります。いずれの場合も、「コンセプトの設定 → 生活者ニーズの調査・分析 → デザインへの落とし込み → 試作 → 納品確認」といったステップを順を追って進めることが重要です。
日硝実業では、お客様の新商品開発をトータルでサポートしています。ヒアリングから企画、発注、生産、納品まで行い、競合との差別化を図り、マーケティング戦略に基づいた最適なパッケージを提案して、商品の魅力を最大限に引き出します。
品質管理体制も万全ですので、安心してご相談ください。














コメント